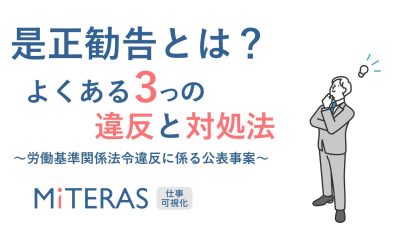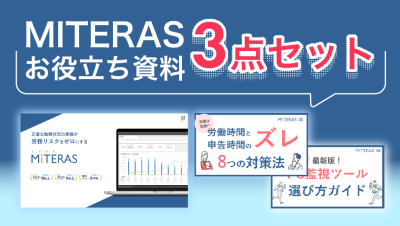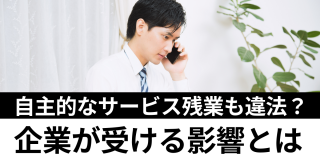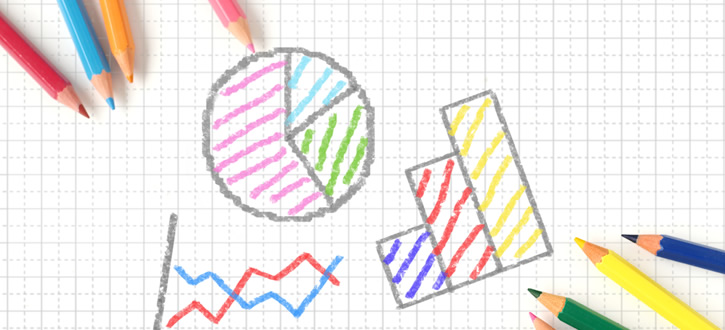働く上で、どうしても残業になってしまうことはありますが、それが長時間に及ぶと、さまざまな問題に発展する可能性があります。働き方改革が推進され、2019年に時間外労働の上限規制が設けられましたが、いまだに残業に関する問題はなくなってはいません。
本記事では、残業が問題視される理由や、それが起こる理由のほか、企業として取り組むべきことなどについて解説します。
目次
1.なぜ残業時間が問題視される?
残業とは、労働基準法でいう「時間外労働」のことを指します。具体的には、1日に8時間、週に40時間を超えて働くことが時間外労働、つまり残業です。
従業員に残業をさせるためには、「時間外、休日労働に関する協定届(36協定)」を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出なければなりません。また、時間外労働には上限があり、「月間45時間以内、年間360時間以内」と定められています。
残業が多すぎれば、さまざまな問題を引き起こします。ただし、労働基準法で定められた残業時間の上限の範囲なら、すぐに問題となることはないでしょう。
問題視されるのは、労働基準法の上限以上の長時間労働です。また、企業の管理外で行われるサービス残業や隠れ残業も、残業の問題としてよく挙げられます。
1-1.残業が引き起こす悪影響
残業が問題死されるのは、さまざまな悪影響を及ぼすことが理由です。まず考えられるのは、従業員の心身の健康へのリスクです。長時間労働による疲労が脳・心臓疾患と関連性が強いことは医学的知見が得られており、精神傷害とも関連すると考えられています。
また、時間外労働の上限規制を超えて労働させれば労働基準法違反となりますし、時間外労働の割増賃金の支払いでコスト増となります。
長時間労働が常態化していることがわかれば採用が難しくなり、離職率が上がる可能性もあるでしょう。もしも過労死などということになれば、大切な従業員を失うだけでなく、企業イメージの低下も避けられません。

MITERAS(ミテラス)仕事可視化は、「勤務状況を正確に把握」できる労務管理ツールです。
勤怠データとPC稼働ログの突合で、法令遵守・はたらき方の見直しを推進できます。
2.なぜ残業問題が起こる?
残業が長時間に及べば、さまざまな問題が引き起こされます。では、なぜそのような長時間の残業が生じるのでしょうか。その理由をご紹介します。
2-1.労働時間を管理できていない
従業員の稼働時間の実態が把握できていなければ、残業問題はなくなりません。勤怠管理を行っていない企業はそうないでしょうが、従業員の稼働実態が把握できていない企業は少なくないものです。
タイムカードや勤怠システム上では退勤してから、サービス残業や隠れ残業を行う従業員がいれば、会社が把握している勤務時間と、実際の稼働時間は乖離してしまいます。いつの間にか長時間労働が行われていて、発覚したときには労働基準法違反になっていたり、過労による疾患を抱えていたりといったことも考えられます。
サービス残業については、下記の記事もご覧ください。
自主的なサービス残業も違法?企業が受ける影響とは
2-2.長時間労働を評価する企業体質
長時間労働を評価する企業体質も、残業問題の原因となるでしょう。「長く働くと意欲が高い」「早く帰る人はやる気がない」「業務量に余裕がある」などと思われれば、従業員は業務として必要性がなくても残業を行ってしまいます。中には、マネジメント層の残業に対する意識が低く、定時にタイムカードの打刻をしてから、さらに働かせるのが慣習となっている企業もあるかもしれません。
業務効率化の取り組みを行っておらず、無駄な会議や打ち合わせが多いといったことも、残業問題が起こる理由です。
無駄な会議の削減については、下記の記事もご覧ください。
無駄な会議の特徴5選|生産性向上にも有効な無駄の解消方法は?
2-3.労働力不足と業務過多
労働力不足は、あらゆる業種・業態で深刻化しています。そういった中で、一人あたりの業務量が増え、残業しなければ仕事が回らない状態になっている企業も少なくないでしょう。
また、繁閑の差が大きい業界などでは、繁忙期に適切な人員配置ができず、一定時期は長時間労働にならざるをえないということもあります。
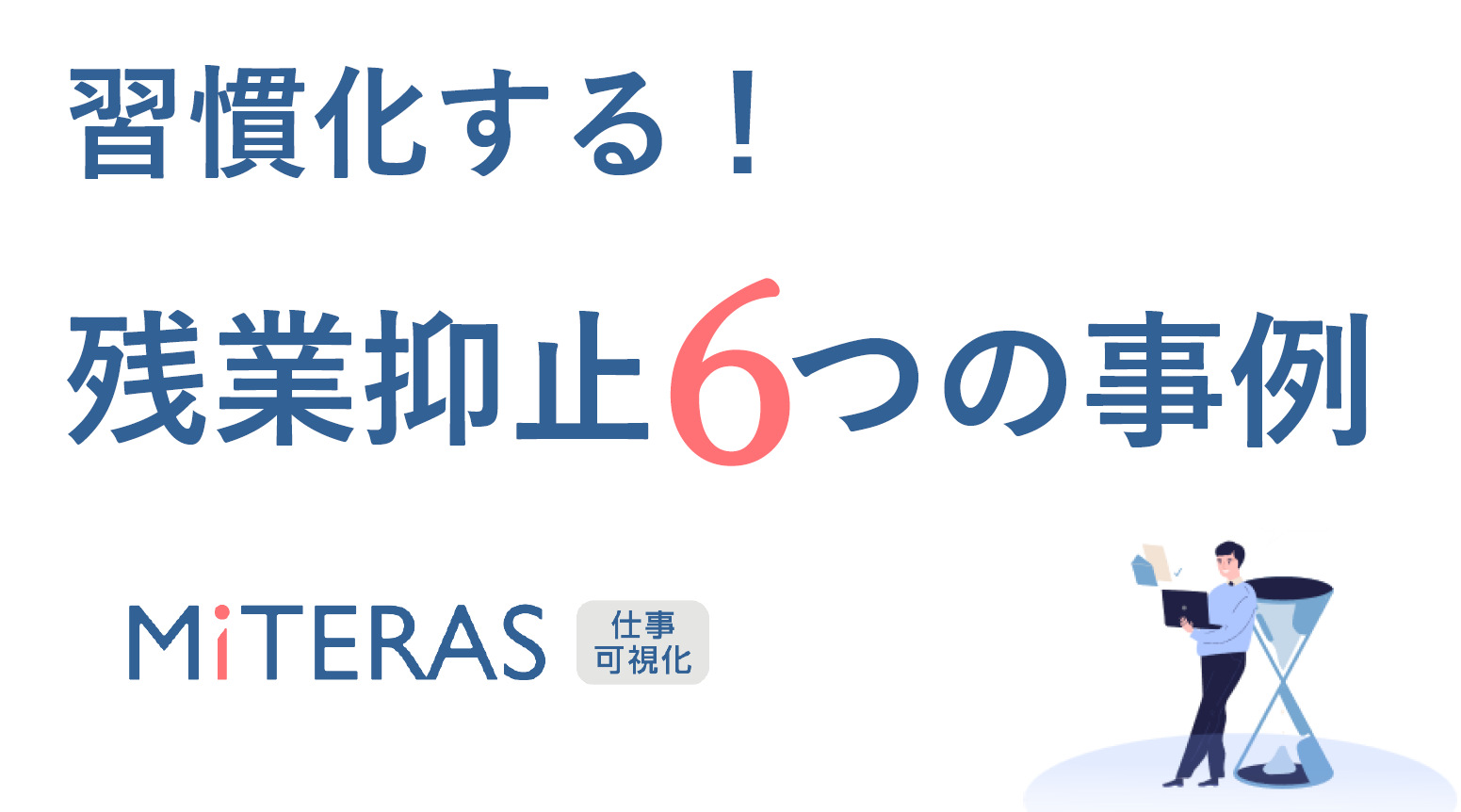
習慣化する!残業抑止6つの事例集
いますぐダウンロードする ➤➤3.残業問題を解決しようとする法改正
ここまで挙げたように、残業はさまざまな問題を引き起こします。政府は、働き方改革の推進とともに、残業問題を解消するため、2019年に働き方改革関連法の改正によって、残業時間の上限規制を設けました。これにより、残業時間の規制が罰則付きの絶対的なものとなっています。業種によっては猶予期間が設けられていますが、それも2024年から適用です。
具体的な残業時間の上限は、前述のように原則として「月間45時間以内、年間360時間以内」と定められています。36協定の特別条項を締結すれば、1年間で6ヵ月以内に限り、月間45時間を超えて残業させることができますが、その場合も下記が限度時間です。
・1年の上限は法定休日労働を除き720時間以内で、これを超える時間の設定はできない
・単月で法定時間外労働と法定休日労働を合わせた限度時間は、100時間未満
・どの2ヵ月ないし6ヵ月を参照しても、時間外・休日労働の平均時間が月80時間以内
※厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
もしも、上限規制を超えて残業をさせた場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。さらに、書類送検されれば、厚生労働省や都道府県の労働局のウェブサイトに企業情報が公表されることになります。
時間外労働については、下記の記事もご覧ください。
時間外労働とは?定義、上限規制について解説
4.企業は残業問題をどう対策すべき?
残業問題を放置すると、罰則が科されるおそれがあるだけでなく、企業のコスト増や従業員の心身への悪影響など、多くのリスクがあります。では、企業はどのように対策すべきなのでしょうか。残業問題に対して企業が行うべきことは、下記のとおりです。
4-1.評価制度の見直し
残業問題の解決には、評価制度の見直しが必要です。中には、残業代を目当てに残業を行っている従業員もいて、削減に協力的ではない場合もあります。残業時間の多さで評価しないことを社内に周知し、さらに評価項目として生産性を取り入れるといいでしょう。
短時間で多くの業務を行ったことや効率良く働けることを評価すれば、「残業時間が減ったから給与が減った」ということになりません。
4-2.強制力のある制度の導入
制度として残業を抑制することも、残業問題の解消に有効です。残業を禁止する日を定める「ノー残業デー」や、上司が承認しなければ残業できない「残業事前申告制」など、強制力のある制度を導入することで、残業時間の削減が可能です。
中には、一定の時間になるとPCが強制シャットダウンするシステムを導入して、残業を抑制する企業もあるようです。
4-3.マネジメント層の意識改革
マネジメント層が残業に対する意識を変えることも、残業問題を解消するために必要なことです。長時間労働を評価する意識があれば、残業時間を削減することはできません。
残業抑制のためには、マネジメント層からの働きかけのほか、業務分担や進捗管理の方法を工夫することが重要です。
4-4.労働時間の可視化
客観的に労働時間を把握することは、残業問題を解決するために必須です。目の届かないところでサービス残業や隠れ残業が行われていては、いつまで経っても長時間の残業はなくなりません。
従業員の申告する勤怠時間だけではなく、実際の稼働時間を把握し、長時間労働になっている場合は適切な業務分担や業務効率化のための指導を行いましょう。
残業問題が抱えるリスクを知って解決に取り組もう
残業問題にはさまざまなリスクがあり、政府も法改正などで解消に取り組んでいます。企業は法律違反にならないため、従業員の健康のため、積極的に解消に取り組まなくてはなりません。評価制度の見直しやマネジメント層の意識改革など、できる範囲から残業問題解消に向けて行動しましょう。
残業問題を解消するためには、「MITERAS仕事可視化」が役立ちます。稼働時間と勤怠の時間を照らし合わせれば、申告のない残業も発見でき、迅速な指導が可能です。PCログを確認されるという意識があれば、それだけで自主的なサービス残業の抑止につなげられます。

監修:MITERAS部
「ホワイトなはたらき方を実現」する労務管理ツール【MITERAS仕事可視化】の担当者によるコラムです。MITERAS仕事可視化は、社員のPC利用の有無、アプリ使用状況などを可視化。勤怠データとPC稼働ログの突合で、法令遵守・はたらき方の見直しを推進できます。当コラムでは、理想の働き方改革実現のポイントから、日常業務の効率化のご提案まで、人事労務のためのお役立ち情報をご紹介します。

MITERAS(ミテラス)仕事可視化は、「勤務状況を正確に把握」できる労務管理ツールです。
勤怠データとPC稼働ログの突合で、法令遵守・はたらき方の見直しを推進できます。