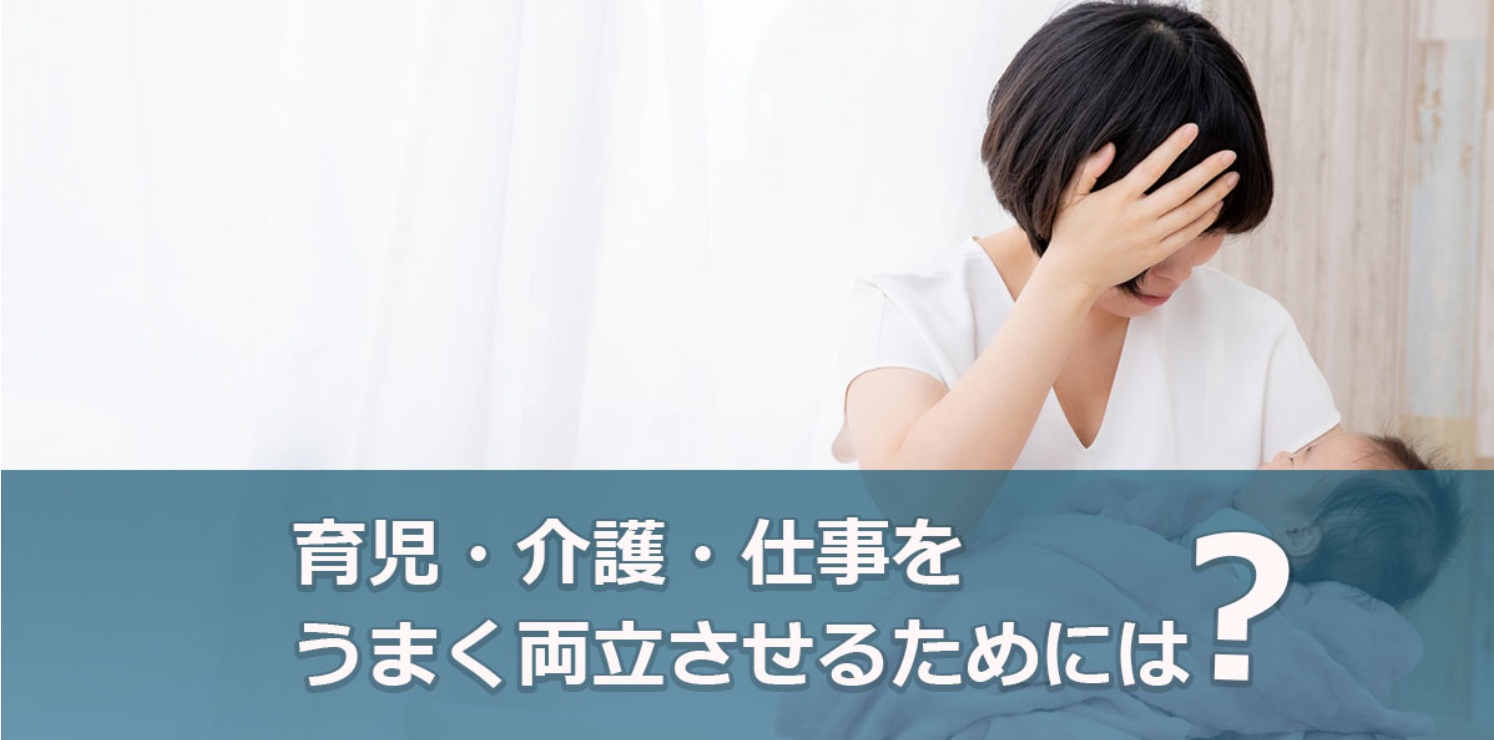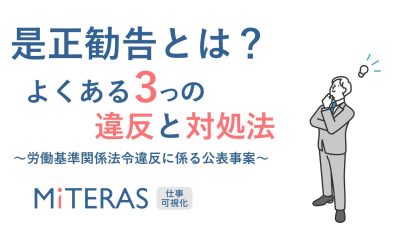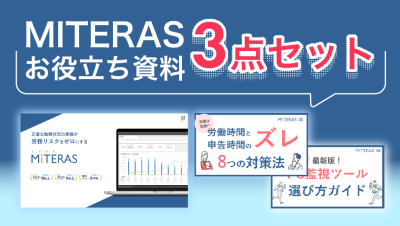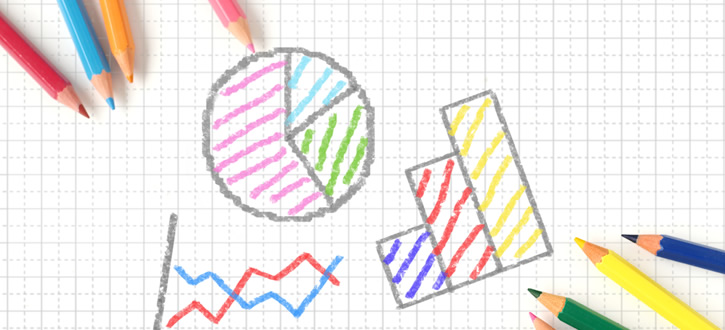共働き世帯の増加と核家族化が進む近年、「育児と仕事」や「介護と仕事」の両立は社会問題となっています。さらに晩婚化の影響により、育児と介護を同時に担う「ダブルケア」が新たな社会問題となりつつあります。
育児・介護の負担増加によって離職を余儀なくされることは、本人はもちろん社会にとって大きな損失です。当記事ではダブルケアの概要、育児・介護と仕事の両立に関する諸問題、両立のポイントについて解説します。
目次
1.育児と介護を並行して行う「ダブルケア」の現状と問題点
ダブルケアとは育児と介護を同時に行うことであり、ダブルケアを行う人はダブルケアラーと呼ばれます。
内閣府の発表によると、平成28年におけるダブルケアラー人口は約25万人でした。この数値は15歳以上で普段育児をしている人の2.5%、普段介護をしている人の4.5%に相当します。また、全ダブルケアラーのうち約17万人は女性でした。
(出典:内閣府男女共同参画局「育児と介護のダブルケアの実態に関する調査」/https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/ikuji_point.pdf)
晩婚化影響で、高齢出産する人が増えました。そのため育児と介護の時期が重なりやすく、以前と比べて親からの育児援助も得にくくなっています。また、兄弟姉妹の平均人数の減少や地域コミュニティの希薄化によって、子ども一人に介護負担が集中しやすくなったこともダブルケア増加の一因です。
多くのダブルケアラーは、以下のような問題を抱えています。
〇精神的な負担がかかりやすい
育児と介護を行うことで日々やることが増えて多忙になり、肉体的にも精神的にも負担が増えます。子どもが大きくなれば育児の手間は減るものの、成長とともに子どもの教育に関する悩みが増えることもあります。一方、介護はいつまで続くかわからず、加齢や病気・事故などで介護の手間が増えることがあります。
また、いわゆるママ友・パパ友コミュニティや介護者向けコミュニティと比べてダブルケアラー向けのコミュニティはまだ少数です。そのため、話を聞いてくれる人が身近におらず、孤立してしまうダブルケアラーも少なくありません。
〇仕事との両立が困難
ダブルケア開始前から就業していた人のうち、ダブルケア開始後に業務量や労働時間を減らした人は男性で18.7%、女性で38.7%でした。なお男性の2.6%、女性の17.5%がダブルケア開始後に離職して無職となっています。
ダブルケアラーが離職や業務量の調整などを余儀なくされる理由は、多忙だけではありません。女性は「家族の支援を得られない」、男性は「介護サービスを利用できない」という回答が最多となり、ダブルケアラーへの理解や支援の少なさがうかがえます。また、「育児や介護は自分ですべき」という回答も多く見られました。
(出典:内閣府男女共同参画局「育児と介護のダブルケアの実態に関する調査」/https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/ikuji_point.pdf)
〇経済的な困窮に陥るリスクが高い
ダブルケアラーは、ダブルケアと仕事の両立の難しさから退職して無収入となるか、あるいは時間に融通が利く代わりに低収入の非正規雇用となる方が多いです。育児・介護サービスを利用しながら働く場合でも、支出が増えることで貯蓄できなくなる状況にもなります。
仕事をしていないダブルケアラーのなかには、育児や介護が一段落してから働きたいと考える人もいます。しかしダブルケアラーの平均年齢は40歳前後であり、介護がいつ終わるかはわかりません。そのため、ダブルケアが落ち着いたときには再就職しにくい状況になっていることもあります。
(出典:内閣府男女共同参画局「育児と介護のダブルケアの実態に関する調査」/https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/ikuji_point.pdf)
これら3つの問題はそれぞれ密接に関わっており、これらの問題からなかなか抜け出せなくなってしまうダブルケアラーも少なくありません。

MITERAS(ミテラス)仕事可視化は、「勤務状況を正確に把握」できる労務管理ツールです。
勤怠データとPC稼働ログの突合で、法令遵守・はたらき方の見直しを推進できます。
2.【育児・介護・仕事】それぞれの「両立」に悩むケース例
家庭の状況によって、さまざまな形の「両立」に悩む人はたくさんいます。
〇育児と仕事の両立
共働き世帯が増えている現在でも、育児や家事の負担は女性に偏る傾向があり、母親がやむなく働き方を変えたり、旧態依然とした企業で働く方は昇進や昇格を諦めたりしまう場合もあります。その一方で、父親が長時間労働等の原因により、思うように家庭に関われないと悩むケースも増えています
また、ひとり親世帯の貧困も社会問題になっています。周囲から育児支援や職場の理解を得られず、思うように働けなくなることが原因として考えられます。
〇介護と仕事の両立
親を介護する人の多くは現役世代のため、介護と仕事の両立は珍しくありません。
ケガや病気などが原因で、それまで元気だった人がいきなり要介護・要支援状態になることがあります。介護の心の準備ができていなかった場合は、誰がどのように介護するか、介護費用を誰が分担するかなどで親族とトラブルになるケースもあります。
核家族の場合は、遠距離介護が必要になることもあります。遠距離介護では介護サービスの利用が不可欠であり、また帰省の頻度が増えて交通費がかさむため、経済的な負担がさらに増えます。
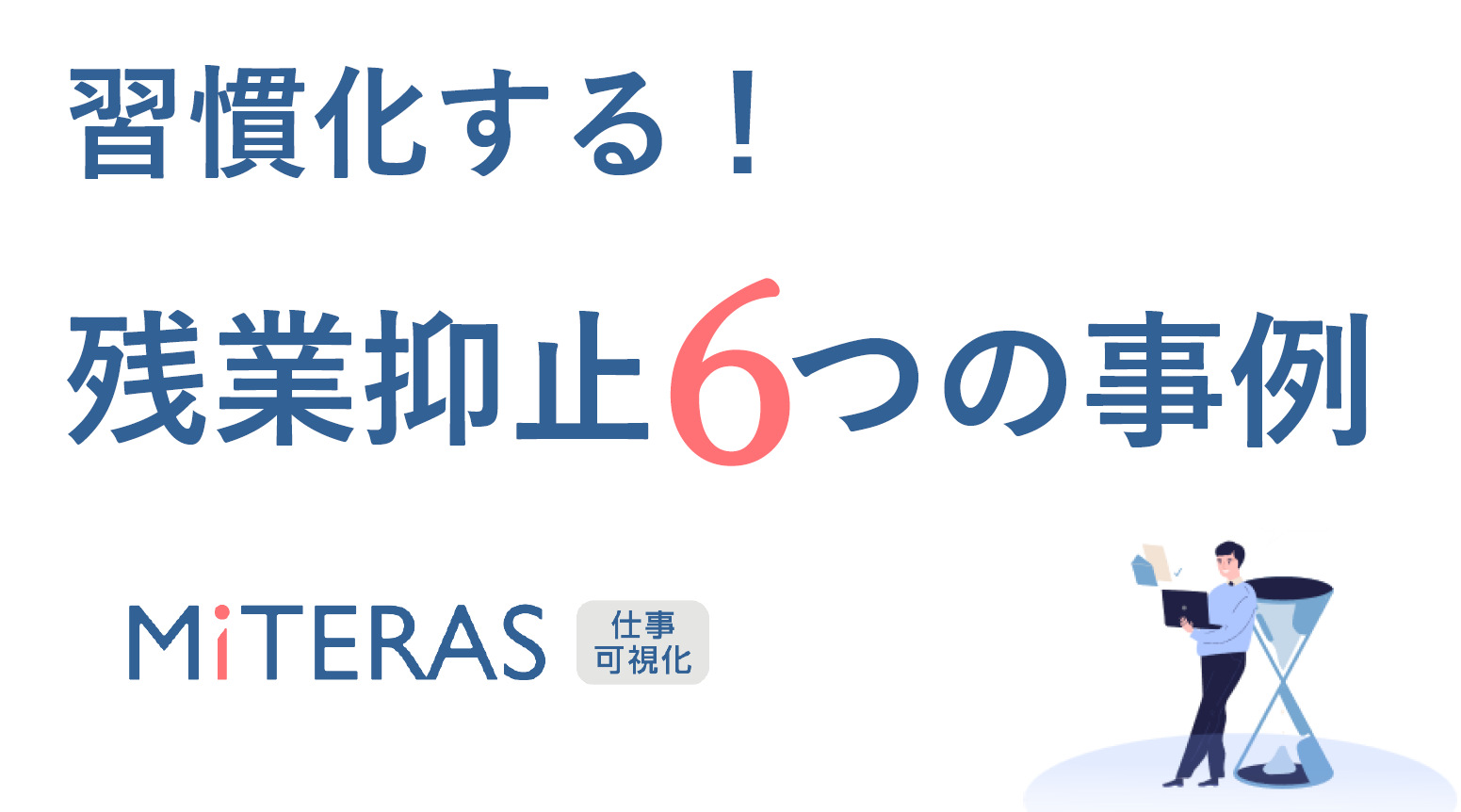
習慣化する!残業抑止6つの事例集
いますぐダウンロードする ➤➤3.育児・介護・仕事をうまく両立させるためには?
内閣府のデータでは、仕事をしていない女性ダブルケアラーの約6割が就業を希望しています。ただし就業希望者の約8割はパート・アルバイトなどの非正規雇用を希望しており、ダブルケアラーが契約期間の定めのない職に就くことの困難さを示しています。
(出典:内閣府男女共同参画局「育児と介護のダブルケアの実態に関する調査」/https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/ikuji_point.pdf)
育児・介護・仕事の両立には、いくつかのポイントがあります。状況によっては実現が難しい場合もありますが、はじめから諦めずにできることから実践してみるとよいでしょう。
3-1.(1)国・行政などの支援を受ける
育児・介護について困ったことやわからないことがあれば、まず自治体の地域包括支援センターや役所の育児・介護関連窓口などへ相談してみましょう。自分に合った支援サービスの紹介を受けたり、育児や介護の経験者に悩みを聞いてもらったりすることができます。
また、厚生労働省公式サイトでも育児や介護と仕事の両立に役立つポータルサイトが紹介されています。それぞれの悩みを持った方へ最適な相談窓口を掲載しているため、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
(出典:厚生労働省「育児・介護と仕事の両立」/https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137518.html)
3-2.(2)介護サービス・保育サービスを利用する
要介護・要支援状態と認められた65歳以上の高齢者や64歳以下の特定疾患患者は、自己負担1~3割で介護保険サービスの利用が可能です。まずケアマネジャーにケアプランを組んでもらい、被介護者本人や家庭の状況に合ったサービスを選びます。要支援状態であれば、介護予防のためのリハビリを活用してもよいでしょう。
要介護・要支援状態でない場合や介護保険でカバーしていない内容のサービスを利用したい場合は、介護保険外サービスもおすすめです。介護保険外サービスの主な内容は、金銭管理・ペットの世話・同居家族がいる場合の家事援助などです。介護保険サービスと比べて費用はかかりますが、介護の負担軽減に役立つでしょう。
育児の負担を減らしたい場合は、保育サービスを積極的に活用しましょう。幼稚園や保育園に通っていない場合は、一時預かりやファミリーサポートを利用して子どもを短時間預けることができます。
一般的に、専業主婦世帯はフルタイム共働き世帯と比べて保育園の利用が難しくなります。ただし、日常的に介護していることを証明できれば専業主婦世帯でも保育園に入れる可能性が高まるでしょう。
3-3.(3)働き方改革を推進している企業で働く
育児・介護と仕事を両立するためには、本人や家族の努力だけでなく企業からのサポートも欠かせません。育児や介護を担う年代の人は仕事で重要なポジションにつくことも多く、退職されると企業にとって大きな損失です。
育児中や介護中でも働きやすい環境を整えるためのポイントは、以下の通りです。
●育児休暇や介護休暇などをとりやすくする
●リモートワークやフレックスタイムを導入する
●時短勤務を導入する
●業務の見直しによって長時間労働を是正し、残業をなくす
●育児・介護およびダブルケアについての相談窓口を設ける
●ひとつの仕事をなるべく複数名で担当し、メンバーが抜けても混乱しにくい体制を整えておく
●時短勤務中や残業が難しい状態でも、本人の希望に合わせて責任ある仕事を任せる
さまざまな背景を持つ人が無理なく働ける環境を整えることで、生産性と定着率の向上につながります。従業員はもちろん顧客や取引先、そして地域社会からもよいイメージを持たれやすくなるでしょう。
3-4.(4)勤務先の休暇制度を利用する
家庭と仕事の両立がどうしても難しい場合は、退職よりも休業や休職をおすすめします。
要介護状態の家族がおり、かつ常時介護を必要とする状態が2週間以上続く場合は、介護休業の取得が可能です。また、原則として満1歳の子どもがいる場合は育児休業を取得できます。一定の条件を満たすと「パパ・ママ育休プラス」が適用され、子どもが1歳2か月に達するまで延長可能です。また育児介護休業法の改正により、2022年4月以降は育児休業の分割取得や休業中の就労が可能になります。
これらの休業制度については法で定められており、原則として雇用主は従業員からの休業取得申請を断ることができません。そして、休業中は収入をカバーするための給付制度が適用されます。
休業制度とは別に、休暇制度を設けている企業も少なくありません。介護休暇は1年間のうち最大5日間、介護対象者が複数いる場合は最大10日間取得できる短期休暇です。一方育児休暇は就学前の子どもを持つ親が育児のために取得できる休暇であり、勤務先によってさまざまな名称があります。
ただしすべての勤務先にこれらの休暇制度があるわけではなく、休暇中の賃金についても明確な決まりはありません。そのため休暇中は無給となる場合もありますが、休暇制度と休業制度を上手に活用することで働き続けやすくなるでしょう。
まとめ
少子高齢化や核家族化などのさまざまな要因によって、特定の人に育児・介護の負担が集中しやすくなっています。さらに近年は育児と介護を同時に担うダブルケアラーが増えており、ダブルケアと仕事を両立できず退職を余儀なくされる人も少なくありません。
育児・介護の負担増によって退職すると経済的困窮に陥りやすくなり、負の連鎖から抜け出しにくくなってしまいます。育児や介護の当事者が無理なく働き続け、かつ企業が人材流出を防いで成長し続けるためには、公的サービスの利用や企業側のサポートが重要な鍵となるでしょう。

監修:MITERAS部
「ホワイトなはたらき方を実現」する労務管理ツール【MITERAS仕事可視化】の担当者によるコラムです。MITERAS仕事可視化は、社員のPC利用の有無、アプリ使用状況などを可視化。勤怠データとPC稼働ログの突合で、法令遵守・はたらき方の見直しを推進できます。当コラムでは、理想の働き方改革実現のポイントから、日常業務の効率化のご提案まで、人事労務のためのお役立ち情報をご紹介します。

MITERAS(ミテラス)仕事可視化は、「勤務状況を正確に把握」できる労務管理ツールです。
勤怠データとPC稼働ログの突合で、法令遵守・はたらき方の見直しを推進できます。